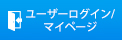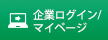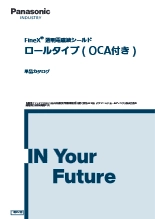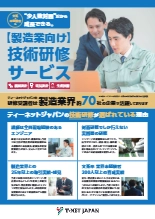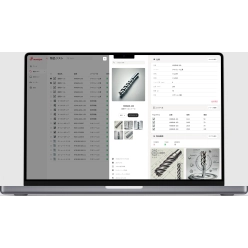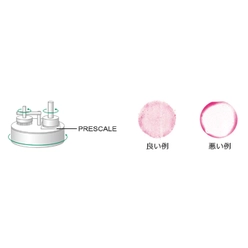超高層建物の長周期地震動対策に有効な減衰装置「iRDT(慣性こま)」を開発
2012/04/09
THK株式会社
株式会社免制震ディバイスとTHK株式会社は、東北大学大学院工学研究科・井上研究室(3月9日現在)の研究を基に、超高層建物の長周期地震動対策に有効な減衰装置『iRDT(Inertial Rotary Damping Tube)』を共同で開発しました。
1.超高層建物の長周期地震による揺れ
超高層建物は揺れの固有周期が長いため、地震波の長周期成分に共振しやすい性質があります。
(※1)。このような揺れは、揺れ幅は大きいものの揺れの速度が遅いため、速度に比例して減衰力を発揮する従来の粘性ダンパーでは、十分な減衰効果を得ることが難しいとされています。
2.『iRDT(慣性こま)』が長周期地震動に効果を発揮するしくみ
今回開発した『iRDT(慣性こま)』は、長周期地震動に有効な効果が得られるよう、従来の粘性減衰装置『RDT(減衰こま)』(※2)を次のように発展させたものです。
1) 回転慣性を増大して利用
『RDT(減衰こま)』の回転部の質量を大きくして筒の外側に配置しました。これにより「回転慣性質量」が大きくなり(※3)、その慣性力を利用した大きなエネルギー吸収が可能になりました。
2)『iRDT(慣性こま)』は、柔軟な「支持バネ」を介して建物に取り付ける
この時、『iRDT(慣性こま)』の回転質量と支持バネの組み合わせによって定まる振動周期と建物自体の固有周期が等しくなるように「支持バネ」の固さを設定します。
超高層建物が長周期地震動によって揺れると『iRDT(慣性こま)』はそれに共振して作動し、建物の揺れよりも大きく(速く)動きます(※4)。粘性抵抗力は速度に比例するため、支持バネを介さずに直接取り付けた場合に比べて大きな抵抗力が発生し、高い減衰効果が得られます。
『iRDT(慣性こま)』は建物の固有周期に共振して動くことで建物全体の揺れのエネルギーを吸収し、超高層建物特有のゆっくり長時間続く揺れを効果的に制御します。
3.『iRDT(慣性こま)』の特長と効果
1) 超高層建物の長周期地震動による揺れ幅を縮小し、揺れの収束時間も短縮
『iRDT(慣性こま)』は、同程度の減衰力を持つオイルダンパーと比べ、建物の揺れ幅を半分程度に抑えることが可能で、揺れの収束時間も短縮します。
2) 減衰装置に関わるコストダウンが可能
在来のオイルダンパーと比較すると、装置単体の価格は『iRDT(慣性こま)』が高価ですが、設置数を減らせるため、建物全体での装置コストは3分の2程度に低減することも可能です。
3) 小型軽量で、新築建物にも既存建物の耐震改修にも利用可能
『iRDT(慣性こま)』の本体は小型(直径40〜60cm、長さ1〜1.5m程度)で、構造体の中に無理なく納まります。また重量は700〜1100kgと軽量で施工性に優れ、建物重量の増加による負荷が少なく済みます。
4) 他の制震装置と併用が可能
5) 設計値を超える過大変形に対しても安全
『iRDT(慣性こま)』は回転すべり機構を内蔵しており(※5)、軸力が一定の値を超えないように制御可能です。想定以上の外力に対しても構造体の過大応力や本体破損の心配がありません。
4.今後の方針
既存および今後計画される超高層建物の長周期地震動対策用の制震装置として販売し、初年度に3億円の売り上げを目指しています。
装置の製造はTHK株式会社、販売は株式会社免制震ディバイスが担当します。
詳しくはこちらをご確認下さい。
(※1) 超高層建物が長周期地震動によって最も大きく揺れるのは、建物がその1次固有周期の地震波に共振する場合です。このとき、建物は上階ほど地面に対する揺れ幅が大きくなります。
超高層建物の1次固有周期は5〜10秒程度と長く、揺れ幅が大きい割には動きがゆっくりしています。
(※2)「RDT(減衰こま)」は回転する筒を内包した減衰装置です。建物が地震等の外力により変形すると、建物に取り付けた「減衰こま」は軸方向に伸縮し、伸縮運動はボールねじ機構により回転運動に変換・増幅されて内筒を回転させます。内筒は粘性流体に包まれており、ここに粘性抵抗力が発生して、装置の軸方向の動き(建物の揺れ)を抑制します。
(※3)『iRDT(慣性こま)』は、「RDT(減衰こま)」の回転部分の内外を入れ替えて、外筒が回転 する機構とし、さらに外筒の径を大きく重くして、大きな回転慣性が発生するしくみになっています。 因みに、直径60cm、回転体質量760kg(本体の総重量約1.1ton)の『iRDT(慣性こま)』の場合、見かけの回転慣性質量は 5400tonになります。この質量が大きいほど、大きな エネルギー吸収が可能になります。
(※4)振動モデルにおいて、質量体が弾性体(バネ要素)を介して取り付けられた組み合わせを「付加振動系」と呼びます。付加振動系は、自身の固有周期に合った動きに対して「与えられた元の動きより大きく運動する(共振現象)」という特徴があります。
『iRDT(慣性こま)』+「支持バネ」は付加振動系を形成し、『iRDT(慣性こま)』は建物自体の揺れの動きより大きく速く運動します。
(※5)回転慣性による質量効果と粘性流体のせん断抵抗による減衰効果を併せ持つ『iRDT(慣性こま)』は、設計上の想定を超える大変形を受けた場合、装置本体やこれに接続する柱などの構造体に過大な応力を発生させる恐れがあります。これを防ぐため『iRDT(慣性こま)』には安全装置として「回転すべり機構」(軸力制限機構)を組み込み、作動時の抵抗力が上限値を超えないようになっています。
1.超高層建物の長周期地震による揺れ
超高層建物は揺れの固有周期が長いため、地震波の長周期成分に共振しやすい性質があります。
(※1)。このような揺れは、揺れ幅は大きいものの揺れの速度が遅いため、速度に比例して減衰力を発揮する従来の粘性ダンパーでは、十分な減衰効果を得ることが難しいとされています。
2.『iRDT(慣性こま)』が長周期地震動に効果を発揮するしくみ
今回開発した『iRDT(慣性こま)』は、長周期地震動に有効な効果が得られるよう、従来の粘性減衰装置『RDT(減衰こま)』(※2)を次のように発展させたものです。
1) 回転慣性を増大して利用
『RDT(減衰こま)』の回転部の質量を大きくして筒の外側に配置しました。これにより「回転慣性質量」が大きくなり(※3)、その慣性力を利用した大きなエネルギー吸収が可能になりました。
2)『iRDT(慣性こま)』は、柔軟な「支持バネ」を介して建物に取り付ける
この時、『iRDT(慣性こま)』の回転質量と支持バネの組み合わせによって定まる振動周期と建物自体の固有周期が等しくなるように「支持バネ」の固さを設定します。
超高層建物が長周期地震動によって揺れると『iRDT(慣性こま)』はそれに共振して作動し、建物の揺れよりも大きく(速く)動きます(※4)。粘性抵抗力は速度に比例するため、支持バネを介さずに直接取り付けた場合に比べて大きな抵抗力が発生し、高い減衰効果が得られます。
『iRDT(慣性こま)』は建物の固有周期に共振して動くことで建物全体の揺れのエネルギーを吸収し、超高層建物特有のゆっくり長時間続く揺れを効果的に制御します。
3.『iRDT(慣性こま)』の特長と効果
1) 超高層建物の長周期地震動による揺れ幅を縮小し、揺れの収束時間も短縮
『iRDT(慣性こま)』は、同程度の減衰力を持つオイルダンパーと比べ、建物の揺れ幅を半分程度に抑えることが可能で、揺れの収束時間も短縮します。
2) 減衰装置に関わるコストダウンが可能
在来のオイルダンパーと比較すると、装置単体の価格は『iRDT(慣性こま)』が高価ですが、設置数を減らせるため、建物全体での装置コストは3分の2程度に低減することも可能です。
3) 小型軽量で、新築建物にも既存建物の耐震改修にも利用可能
『iRDT(慣性こま)』の本体は小型(直径40〜60cm、長さ1〜1.5m程度)で、構造体の中に無理なく納まります。また重量は700〜1100kgと軽量で施工性に優れ、建物重量の増加による負荷が少なく済みます。
4) 他の制震装置と併用が可能
5) 設計値を超える過大変形に対しても安全
『iRDT(慣性こま)』は回転すべり機構を内蔵しており(※5)、軸力が一定の値を超えないように制御可能です。想定以上の外力に対しても構造体の過大応力や本体破損の心配がありません。
4.今後の方針
既存および今後計画される超高層建物の長周期地震動対策用の制震装置として販売し、初年度に3億円の売り上げを目指しています。
装置の製造はTHK株式会社、販売は株式会社免制震ディバイスが担当します。
詳しくはこちらをご確認下さい。
(※1) 超高層建物が長周期地震動によって最も大きく揺れるのは、建物がその1次固有周期の地震波に共振する場合です。このとき、建物は上階ほど地面に対する揺れ幅が大きくなります。
超高層建物の1次固有周期は5〜10秒程度と長く、揺れ幅が大きい割には動きがゆっくりしています。
(※2)「RDT(減衰こま)」は回転する筒を内包した減衰装置です。建物が地震等の外力により変形すると、建物に取り付けた「減衰こま」は軸方向に伸縮し、伸縮運動はボールねじ機構により回転運動に変換・増幅されて内筒を回転させます。内筒は粘性流体に包まれており、ここに粘性抵抗力が発生して、装置の軸方向の動き(建物の揺れ)を抑制します。
(※3)『iRDT(慣性こま)』は、「RDT(減衰こま)」の回転部分の内外を入れ替えて、外筒が回転 する機構とし、さらに外筒の径を大きく重くして、大きな回転慣性が発生するしくみになっています。 因みに、直径60cm、回転体質量760kg(本体の総重量約1.1ton)の『iRDT(慣性こま)』の場合、見かけの回転慣性質量は 5400tonになります。この質量が大きいほど、大きな エネルギー吸収が可能になります。
(※4)振動モデルにおいて、質量体が弾性体(バネ要素)を介して取り付けられた組み合わせを「付加振動系」と呼びます。付加振動系は、自身の固有周期に合った動きに対して「与えられた元の動きより大きく運動する(共振現象)」という特徴があります。
『iRDT(慣性こま)』+「支持バネ」は付加振動系を形成し、『iRDT(慣性こま)』は建物自体の揺れの動きより大きく速く運動します。
(※5)回転慣性による質量効果と粘性流体のせん断抵抗による減衰効果を併せ持つ『iRDT(慣性こま)』は、設計上の想定を超える大変形を受けた場合、装置本体やこれに接続する柱などの構造体に過大な応力を発生させる恐れがあります。これを防ぐため『iRDT(慣性こま)』には安全装置として「回転すべり機構」(軸力制限機構)を組み込み、作動時の抵抗力が上限値を超えないようになっています。