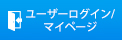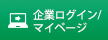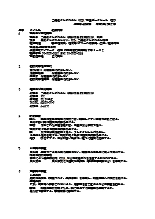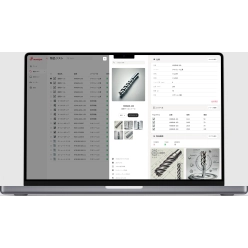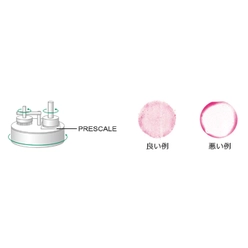DOCSIS 3.1テストソリューション群を発表
2014/10/30
キーサイト・テクノロジー株式会社
東京、2014年8月8日発 - キーサイト・テクノロジー合同会社(職務執行者社長:梅島 正明、本社:東京都八王子市高倉町9番1号)は、Data Over Cable Service Interface Specification (DOCSIS)の評価向けとして、最大192MHz(メガヘルツ)帯域の信号生成・解析に対応したハードウェアならびにソフトウェアを発表します。このテストソリューションは、DOCSIS 3.1仕様に準拠した送受信機および部品の開発エンジニアに最適です。
DOCSIS規格は、世界各国のケーブルテレビ事業者および加入者のニーズに応えるべく進化を続けています。高解像度テレビ(HDTV)、家庭内ビデオストリーミング、室内ゲームなど、最新のアプリケーションにより、数ギガビットのデータレートの需要が高まっています。広帯域化へのニーズの高まりを受け、DOCSIS規格のバージョン3.1が策定されました。
DOCSIS 3.1は、直交周波数分割多重(OFDM)や低密度パリティーチェック(LPDC)前方誤り訂正(FEC)技術などの活用により、高速・大容量化を実現しています。新たに策定されたDOCSIS 3.1の主な仕様は以下のとおりです。
●同一スペクトラム上で、最大50 %のスループット向上
●アップストリーム側2.5Gbps(ギガビット/秒)
●既存のHFC (hybrid fiber-coaxial)ネットワークでダウンストリーム側10 Gbpsを実現
DOCSIS 3.1の効率的なスペクトラム利用により、ビットあたりのデータ伝送コストを劇的に低減しています。ケーブルテレビ事業者は低コストで大容量・高速化を実現可能となります。これは、衛星や無線を使った事業者に比べて利点となります。
キーサイト・テクノロジーの最高技術責任者であるJay Alexanderは次のように語っています。
「DOCSIS 3.1規格は大幅な大容量・高速化を実現する一方で、設計やテストにおいては新たな課題が山積しています。当社のDOCSIS3.1テストソリューション群は複雑なOFDM、LDPC、FECに対応しているのはもちろん、従前のDOCSIS技術もサポートしています。」
DOCSIS 3.1対応の送受信機や部品の設計、ならびにその性能の評価においては、厳格な試験が必要となります。規格化団体では新技術を採用しながら、従来の規格との後方互換性確保も求めていることが、設計・評価を困難にしている理由の1つです。当社ではDOCSIS 3.1のテストに必要となるハードウェアおよびソフトウェアを提供することで、このような課題に対応しています。
■信号生成
DOCSIS 3.1の信号生成においては、大容量メモリ、最大5 GHz帯域幅、優れたスプリアスフリー・ダイナミックレンジ (SFDR) を実現したM8190A 任意波形発生器 (AWG)を提供しています。これにより、M8190Aは最大192MHz帯域でDOCSIS 3.1の信号に現実のネットワークにおける信号ストレスを再現することが可能で、既存のHFCネットワーク上で伝送試験を行うことができます。
M8190A AWGとM9099 波形生成アプリケーションソフトウェアを組み合わせることで、コード化前のDOCSIS3.1波形の生成が可能です。これは部品レベルのテストに適しています。またESL設計ソフトウェアであるSystemVueでは、コード化されたDOCSIS3.1送受信シミュレーションライブラリーを提供しています。このライブラリーは、M8190A AWGで波形を発生させたり、LDPCデコードでのBERT試験を実行したりする際に利用します。さらに、SystemVueは、DOCSIS 3.1送信環境にノイズ(LTE信号など)を付加してシミュレーションを行う用途にも適しています。
■信号解析
DOCSIS 3.1の信号解析には、M9703A 8チャネルAXIe高速デジタイザー、もしくはその2チャネル版であるU5303A PCIe 12ビット高速デジタイザーにより、DCから2 GHzまでの幅広い入力信号に対応可能です。チャネルインタリーブ機能により、M9703Aもしくは1チャネル構成のU5303Aで、4チャネル構成が可能となります。これにより、DCから1.4 GHzまでのDOCSIS 3.1波形を、優れたダイナミックレンジで捕捉することが可能です。
複数の測定に対応した89600 VSAソフトウェアは、192 MHz帯域を超える変調解析機能を提供しています。89600 VSAはOFDM技術のテストに広く使われています。SystemVueのDOCSISライブラリーおよびコード化BER試験機能では、DOCSIS 3.1の下り信号の復調およびデコードが可能です。
スペクトラム解析には、160 MHz帯域を実現し、様々な解析機能を提供するN9020A MXAおよびN9030A PXAシグナル・アナライザが最適です。DOCSIS 3.1の上り、下りの信号を狭い帯域で解析できます。
DOCSIS規格は、世界各国のケーブルテレビ事業者および加入者のニーズに応えるべく進化を続けています。高解像度テレビ(HDTV)、家庭内ビデオストリーミング、室内ゲームなど、最新のアプリケーションにより、数ギガビットのデータレートの需要が高まっています。広帯域化へのニーズの高まりを受け、DOCSIS規格のバージョン3.1が策定されました。
DOCSIS 3.1は、直交周波数分割多重(OFDM)や低密度パリティーチェック(LPDC)前方誤り訂正(FEC)技術などの活用により、高速・大容量化を実現しています。新たに策定されたDOCSIS 3.1の主な仕様は以下のとおりです。
●同一スペクトラム上で、最大50 %のスループット向上
●アップストリーム側2.5Gbps(ギガビット/秒)
●既存のHFC (hybrid fiber-coaxial)ネットワークでダウンストリーム側10 Gbpsを実現
DOCSIS 3.1の効率的なスペクトラム利用により、ビットあたりのデータ伝送コストを劇的に低減しています。ケーブルテレビ事業者は低コストで大容量・高速化を実現可能となります。これは、衛星や無線を使った事業者に比べて利点となります。
キーサイト・テクノロジーの最高技術責任者であるJay Alexanderは次のように語っています。
「DOCSIS 3.1規格は大幅な大容量・高速化を実現する一方で、設計やテストにおいては新たな課題が山積しています。当社のDOCSIS3.1テストソリューション群は複雑なOFDM、LDPC、FECに対応しているのはもちろん、従前のDOCSIS技術もサポートしています。」
DOCSIS 3.1対応の送受信機や部品の設計、ならびにその性能の評価においては、厳格な試験が必要となります。規格化団体では新技術を採用しながら、従来の規格との後方互換性確保も求めていることが、設計・評価を困難にしている理由の1つです。当社ではDOCSIS 3.1のテストに必要となるハードウェアおよびソフトウェアを提供することで、このような課題に対応しています。
■信号生成
DOCSIS 3.1の信号生成においては、大容量メモリ、最大5 GHz帯域幅、優れたスプリアスフリー・ダイナミックレンジ (SFDR) を実現したM8190A 任意波形発生器 (AWG)を提供しています。これにより、M8190Aは最大192MHz帯域でDOCSIS 3.1の信号に現実のネットワークにおける信号ストレスを再現することが可能で、既存のHFCネットワーク上で伝送試験を行うことができます。
M8190A AWGとM9099 波形生成アプリケーションソフトウェアを組み合わせることで、コード化前のDOCSIS3.1波形の生成が可能です。これは部品レベルのテストに適しています。またESL設計ソフトウェアであるSystemVueでは、コード化されたDOCSIS3.1送受信シミュレーションライブラリーを提供しています。このライブラリーは、M8190A AWGで波形を発生させたり、LDPCデコードでのBERT試験を実行したりする際に利用します。さらに、SystemVueは、DOCSIS 3.1送信環境にノイズ(LTE信号など)を付加してシミュレーションを行う用途にも適しています。
■信号解析
DOCSIS 3.1の信号解析には、M9703A 8チャネルAXIe高速デジタイザー、もしくはその2チャネル版であるU5303A PCIe 12ビット高速デジタイザーにより、DCから2 GHzまでの幅広い入力信号に対応可能です。チャネルインタリーブ機能により、M9703Aもしくは1チャネル構成のU5303Aで、4チャネル構成が可能となります。これにより、DCから1.4 GHzまでのDOCSIS 3.1波形を、優れたダイナミックレンジで捕捉することが可能です。
複数の測定に対応した89600 VSAソフトウェアは、192 MHz帯域を超える変調解析機能を提供しています。89600 VSAはOFDM技術のテストに広く使われています。SystemVueのDOCSISライブラリーおよびコード化BER試験機能では、DOCSIS 3.1の下り信号の復調およびデコードが可能です。
スペクトラム解析には、160 MHz帯域を実現し、様々な解析機能を提供するN9020A MXAおよびN9030A PXAシグナル・アナライザが最適です。DOCSIS 3.1の上り、下りの信号を狭い帯域で解析できます。