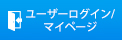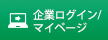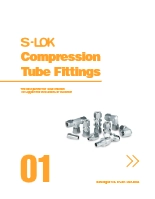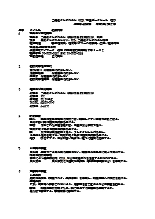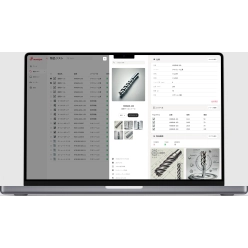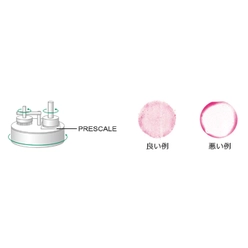岩手大とチノー、生物から学んだ制御アルゴリズムを用いた温度調節計を開発
2010/11/19
(株)チノー
岩手大学(伊藤菊一研究室、長田洋研究室)と株式会社チノー(社長 苅谷嵩夫)は、植物の発熱システムに注目し、世界で初めて植物が持つ温度制御アルゴリズムを用いた温度調節計を開発し、チノーの汎用温度調節計のDBシリーズに搭載した。開発した調節計は、温度整定時間の短縮や高いオーバーシュート抑制効果等を発揮し、制御対象により大幅な省エネ効果も期待できる産業用温度調節計である。
生物から学んだ制御アルゴリズム(ザゼンソウ制御)を搭載した調節計は、地域性のある研究素材に端を発した産学連携研究成果ということに留まらず、生物の繊細な代謝機能を模倣した工業化研究の成功例として、社会に大きなインパクトを与えるものである。
このザゼンソウ制御は、半導体制御装置(拡散炉・ア二−ル炉)、金属熱処理炉制御装置、恒温恒湿槽・恒温恒湿室制御装置、オートクレーブ(化学反応釜)、空調設備といった分野にて既に省エネ・オーバシュート抑制といった成果をあげており、今後、用途と適用分野を広げ、省エネ効果に貢献できる商品として、拡販していく。
【ザゼンソウとは】
ザゼンソウは、ミズバショウと同じ仲間のサトイモ科の多年草であり、早春に花を咲かせる。このザゼンソウは、植物でありながら、肉穂花序(にくすいかじょ)と呼ばれる器官で発熱が観察される。
ザゼンソウには、自身で雌期・両性期・雌期を持つ雌雄異熟(しゆういじゅく)と呼ばれる特徴がある。非常に興味深いことに、雌期における肉穂花序は、氷点下を含む外気温の変動にも関わらず、発熱によりその体温をほぼ20℃に維持することができる。このような肉穂花序における温度制御は、1週間程度も持続することが知られており、群生地において、肉穂花序の発熱により周囲の雪を融かしている様子を観察することができる。
【開発・商品化の経緯】
本調節計は、1998年に岩手大学農学部において伊藤菊一教授により開始されたザゼンソウの植物学的な発熱研究に端を発し、2004年より岩手大学工学部との農工連携研究、2007年より岩手大学地域連携推進センターを介したチノーとの産学連携研究を経て、その開発・商品化を行った。なお、伊藤教授の研究は、独立行政法人・生物系特定産業技術研究推進センターの基礎研究推進事業(2001年〜2005年)、文部科学省の21世紀COEプログラム(2004年〜2009年)などの学術的研究として進められた。
【ザゼンソウ制御の特長】
ザゼンソウの発熱機構の制御アルゴリズムは、生命現象の解析によって得られた情報に基づいたものである。ザゼンソウ制御は、従来の制御アルゴリズムで動作する調節計に比べて、制御量(現在値)を“無駄なく迅速に”設定値に到達させることができ、「高いロバスト性(堅牢性)」と「高い省エネルギー特性」を両立させたこれまでにない優れた制御性能を発揮する。
■オーバーシュート抑制
汎用的に用いられているPIDと呼ばれる制御では、操作対象により設定した目標値になかなか到達しない、設定より高くなる(オーバーシュート)などの問題があり、安定するまでの時間(整定時間)が長くなる場合には、これを補うために様々な補償アルゴリズムが追加されている。今回開発したザゼンソウ制御では、制御量の変化から“その到達値を予測”して制御を行い、最適な操作量を出力するアルゴリズムであるため、整定時間を保ちつつオーバーシュートを発生し難い、という大きな特長を持つ。
■外乱抑制
暖房空調されている空間のドア開閉時のように、“外乱”とよばれる急激な温度の変化がある場合、従来制御では、早く復帰させようと過度に出力するため、かえって制御が乱れてしまう場合がある。ザゼンソウ制御の方式では、復帰後に温度が設定値を超えるかどうかを予測して制御を行うため、過度な出力を行なわず、安定した制御が可能になる。
■省エネ
ザゼンソウ制御は制御対象の熱的特性を捕らえて、それぞれに適した操作量を出力する。このため、無駄なエネルギーの投入が避けられ、たとえば加熱/冷却と加湿/除湿機能を併有する恒温恒湿槽の場合には、高い省エネルギー特性が期待できる。
生物から学んだ制御アルゴリズム(ザゼンソウ制御)を搭載した調節計は、地域性のある研究素材に端を発した産学連携研究成果ということに留まらず、生物の繊細な代謝機能を模倣した工業化研究の成功例として、社会に大きなインパクトを与えるものである。
このザゼンソウ制御は、半導体制御装置(拡散炉・ア二−ル炉)、金属熱処理炉制御装置、恒温恒湿槽・恒温恒湿室制御装置、オートクレーブ(化学反応釜)、空調設備といった分野にて既に省エネ・オーバシュート抑制といった成果をあげており、今後、用途と適用分野を広げ、省エネ効果に貢献できる商品として、拡販していく。
【ザゼンソウとは】
ザゼンソウは、ミズバショウと同じ仲間のサトイモ科の多年草であり、早春に花を咲かせる。このザゼンソウは、植物でありながら、肉穂花序(にくすいかじょ)と呼ばれる器官で発熱が観察される。
ザゼンソウには、自身で雌期・両性期・雌期を持つ雌雄異熟(しゆういじゅく)と呼ばれる特徴がある。非常に興味深いことに、雌期における肉穂花序は、氷点下を含む外気温の変動にも関わらず、発熱によりその体温をほぼ20℃に維持することができる。このような肉穂花序における温度制御は、1週間程度も持続することが知られており、群生地において、肉穂花序の発熱により周囲の雪を融かしている様子を観察することができる。
【開発・商品化の経緯】
本調節計は、1998年に岩手大学農学部において伊藤菊一教授により開始されたザゼンソウの植物学的な発熱研究に端を発し、2004年より岩手大学工学部との農工連携研究、2007年より岩手大学地域連携推進センターを介したチノーとの産学連携研究を経て、その開発・商品化を行った。なお、伊藤教授の研究は、独立行政法人・生物系特定産業技術研究推進センターの基礎研究推進事業(2001年〜2005年)、文部科学省の21世紀COEプログラム(2004年〜2009年)などの学術的研究として進められた。
【ザゼンソウ制御の特長】
ザゼンソウの発熱機構の制御アルゴリズムは、生命現象の解析によって得られた情報に基づいたものである。ザゼンソウ制御は、従来の制御アルゴリズムで動作する調節計に比べて、制御量(現在値)を“無駄なく迅速に”設定値に到達させることができ、「高いロバスト性(堅牢性)」と「高い省エネルギー特性」を両立させたこれまでにない優れた制御性能を発揮する。
■オーバーシュート抑制
汎用的に用いられているPIDと呼ばれる制御では、操作対象により設定した目標値になかなか到達しない、設定より高くなる(オーバーシュート)などの問題があり、安定するまでの時間(整定時間)が長くなる場合には、これを補うために様々な補償アルゴリズムが追加されている。今回開発したザゼンソウ制御では、制御量の変化から“その到達値を予測”して制御を行い、最適な操作量を出力するアルゴリズムであるため、整定時間を保ちつつオーバーシュートを発生し難い、という大きな特長を持つ。
■外乱抑制
暖房空調されている空間のドア開閉時のように、“外乱”とよばれる急激な温度の変化がある場合、従来制御では、早く復帰させようと過度に出力するため、かえって制御が乱れてしまう場合がある。ザゼンソウ制御の方式では、復帰後に温度が設定値を超えるかどうかを予測して制御を行うため、過度な出力を行なわず、安定した制御が可能になる。
■省エネ
ザゼンソウ制御は制御対象の熱的特性を捕らえて、それぞれに適した操作量を出力する。このため、無駄なエネルギーの投入が避けられ、たとえば加熱/冷却と加湿/除湿機能を併有する恒温恒湿槽の場合には、高い省エネルギー特性が期待できる。