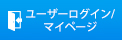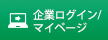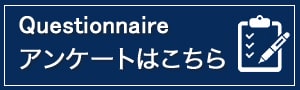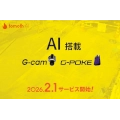【動画】Analog Devices特別講座
【Analog Devices特別講座】 基本をがっちり!
アナログ電子回路30選~OPアンプの活用から重要テクニックまで〜
本動画シリーズは「Analog Devices特別講座」として、アナログ・デバイセズ社のプリンシパルエンジニア
である石井聡氏が、実務ですぐに役立つ「定番回路」に絞って、アナログ回路設計に欠かせないキー・デバイス「OPアンプ」について、基礎から実践まで丁寧に解説します。
OPアンプの基本的な役割から、実際の設計現場で求められる発振対策まで、体系的かつ実践的に学べる構成となっており、LTspiceを用いたシミュレーションを通じて、実際の設計データを動かしながら理解を深めることができます。
アナログ回路の初学者はもちろん、改めてOPアンプ設計の基本を見直したいエンジニアにも最適な、信頼性と実用性を兼ね備えた内容となっています。
■第1回 OPアンプの中身
OPアンプの中身は3つのブロックから構成されているということを説明します。たくさんのトランジスタが集積されたOPアンプICも、たった3つのブロックから構成されているのだという視野に立てば、その動作の理解がスムースになります。
■第2回 OPアンプの基本回路
一般的によく使われるOPアンプによる増幅回路を3種類示し、それぞれの設計方法や得失について説明します。単純な回路動作の説明ではなく、実際の回路として応用できるように、グラウンドを基準とした単電源回路(つまり負電源が不要な回路)について説明します。
■第3回 OPアンプの基本的な各種特性
OPアンプ回路を構築するうえで、かならず知っておかなければならない動作のしくみと特性について説明します。内容としては周波数特性をメインに説明し、小信号の場合と大信号の場合の周波数特性の違いについて説明します。また動作電圧範囲も説明し、低電圧の単電源回路での活用についての指針を示します。
■第4回 オーディオ用回路
単純かつ基本的なオーディオ用回路について説明します。オーディオ信号は直流からの増幅が不要なため、簡易な回路を構成できます。またミキシング回路と周波数特性と、パワー段のドライブの説明では意外な事実をご紹介します。
■第5回 高精度計測回路
高精度な計測を行いたい場合のアナログ信号の増幅について説明します。実際のOPアンプには各種誤差要因があるので、まずその説明から始まり、誤差要因を考えたうえでの計測に適したOPアンプの種類を解説します。また差電圧を検出することの多い計測において、どのような回路が利用できるか、そしてその注意点についても解説します。
■第6回 OPアンプで作る発振回路
OPアンプで作る発振回路の例を3種類紹介します。発振回路には弛張発振と帰還形発振の2種類があります。それぞれを説明し、帰還形発振回路では「バルクハウゼンの発振条件」という、発振回路を安定に動作させるための条件を解説しながら、ふたつの回路例を見ていきます。ストーリとしてはウイーン・ブリッジ発振回路がおススメということになっています。
■第7回 フォトダイオード電流増幅(電流電圧変換回路)
フォトダイオードは、光を電気(電流)信号に変換する素子ですが、これを目的とする電圧に変換し、目的とする増幅特性を実現する必要があります。ここではフォトダイオード信号を増幅する回路(トランスインピーダンス・アンプ、TIA)を紹介し、その課題について言及します。課題の1つは安定性で、もう1つはノイズ特性です。それぞれフォトダイオードの「接合容量」というものが悪さの根源となっていることが理解いただけます。
■第8回 OPアンプの安定性の確認と改善方法
まとめの意味も含めて、重要なOPアンプの安定性について解説します。ここでいう安定性とはOPアンプの出力がブルブルと震えてしまったり、異常発振しないかということを指します。設計したOPアンプ回路がどんな条件(温度、電源電圧、負荷など)でも安定に動作するか、また複数台生産した回路がすべて安定に動くかを「位相余裕」という指標から考えていきます。